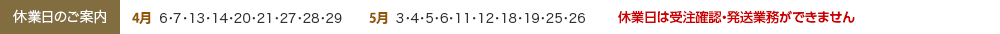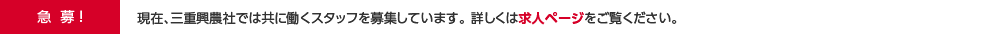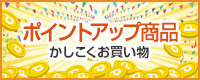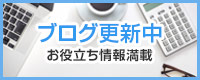今年も、連日カメムシの大量発生、その被害のニュースや記事を目にします。また、各地で注意報も出ています。
カメムシから農作物守るために、カメムシを知っていただきその対策を実践してほしいです!

カメムシとは…
学術的には、「カメムシ」という名称の昆虫は存在しません。
カメムシ目に属する昆虫の総称を、一般名称としてカメムシと呼びます。
さまざまな種類がいますが、体長は1〜2.5cmほどで、体色は緑色や褐色であることが多いです。
強烈なニオイを放つことから、「クサムシ」や「ヘコキムシ」と呼ばれることもあります。
カメムシが発生する原因は、主に2つ
-
植物が生い茂る空き地がある。
-
暖かい気温。
カメムシが発生する原因の1つ目が、産卵と食事ができる草花が生い茂った空き地の存在です。
植物が生い茂っていることで、果実や花の蜜はカメムシの食事になり、繁殖・産卵の場としても最適となります。
空き地で増えたカメムシは、食事を求めて庭やベランダに飛来するため、農家や一般家庭に被害をもたらします。
暖かい気温も、カメムシが発生する原因とされています。
カメムシの産卵期は6月で、7月の気温が高くなる頃には孵化して幼虫となり、脱皮を繰り返しながら9月には成虫に。
11月頃まで活発に行動し、被害を広げます。
カメムシの寿命は1年半といわれており落ち葉の下や草の根元などで越冬します。
越冬した成虫が春になると活動を再開して農作物に被害をもたらします。

カメムシによる被害が多い主な作物
-
枝豆
-
大豆
-
かぼちゃ
-
じゃがいも
-
ナス
-
ピーマン
-
トマト
-
梨
-
りんご
-
オクラ
-
パプリカ
-
アンズ
-
桃
-
水稲
など草花や樹木も好むのが特徴です。
カメムシがもたらす農作物や植物に対する被害
カメムシは吸汁性のため、柔らかく水分の多い部分を好みます。
そのため果実や新芽、茎葉などに食害が多く発生します。
カメムシに汁を吸われてしまった果実は、腐敗したり変形したりして、売り物になりません。
またカメムシの臭いが果実に移り、食べることができなくなってしまいます。
新芽が吸汁されると、芽が折れたり曲がったりします。
茎葉の場合は、奇形化したり穴が空いたりするなどの被害が発生します。
被害が大きい場合は、生育不良になってしまうこともあるので、注意が必要です。
被害例・・・トマト・ピーマン

カメムシの食害にあったトマト


ピーマンの葉裏と茎


ピーマンの葉裏に産卵
この先、7月~9月は要注意をお願いします!
エダマメに付着するカメムシ類
写真1(YK)

写真2(YK)

写真3(HT)

写真4(YK)

食害するカメムシ
エダマメには多くのカメムシ類が発生し、主なものはホソヘリカメムシ(写真1:成虫)、イチモンジカメムシ(写真2:成虫)、アオクサカメムシ(写真3:幼虫)、ミナミアオカメムシの4種類である。
ホソヘリカメムシの成虫は褐色の1.5センチくらいの虫で、細長く、脚が長く、アブのような感じでよく飛ぶ。イチモンジカメムシは薄緑色の1センチくらいの虫で、頭のすぐ後ろに白色または赤色の横帯がある。アオクサカメムシとミナミアオカメムシは緑色の1.5センチくらいの虫で、頭の後ろの横帯はありません。いずれも幼虫は背中に翅がなく、その部分にさまざまな模様があります。(写真3)。
被害
花が終わって莢ができるころに汁が吸われ、莢の生長が止まって落下する。
豆の肥大が始まってから汁が吸われた場合は、不規則にゆがんだ豆や一部が褐色に変色した豆となってしまいます。
生態
3種類とも成虫が越冬し、春から秋まで2~3回発生を繰り返します。7~9月に多発し、収穫期の遅いエダマメで被害が多くなります。
3種類ともマメ科作物のほか、さまざまな作物、雑草の種子の汁を吸って暮らしています。成虫は飛ぶ力が強く、遠方からも侵入してきます。
被害が毎年多い(成虫の飛び込みの多い)畑と、そうでない畑があります。また、年によって被害程度が大きく異なります。
農林水産省掲示の情報もご覧ください。
1.果樹カメムシ類
果樹類(かんきつ、りんご、なし、もも及びかき等)に被害を与えるカメムシ類は、主にチャバネアオカメムシ、クサギカメムシ、ツヤオアカメムシが知られています。
これらカメムシ類は、山林に生息してスギやヒノキ等の球果を餌に繁殖し、山林での餌が不足すると果樹園に飛来して果実を吸汁することで落果や奇形果等の被害を与えます。

チャバネアオカメムシ

クサギカメムシ
2.斑点米カメムシ類

アカスジカスミカメ

アカヒゲホソミドリカスミカメ

フタトゲムギカスミカメ
籾を加害し、黒色または茶色の斑点ができた玄米(斑点米)を生ずるカメムシ類を総称して「斑点米カメムシ類」と呼びます。
多くの種が水田周辺の雑草に生息し、出穂期になると水田に侵入し穂を加害します。
3.イネカメムシ

イネカメムシ
斑点米カメムシ類の一種であるイネカメムシは、斑点米を発生させる他、不稔米を発生させる害虫で、近年、発生量が増加傾向にあります。
農林水産省資料 参考
愛知県:三重県の病害虫情報もご覧ください
※上記は、愛知県と三重県の情報ですのでご注意してください。
カメムシ類の防除に効果的な農薬はこちら
カメムシ類の生育、活動密度を低減するために定期的な除草が大切です。
特に、水稲では出穂前に畦畔等の除草を行いましょう。
除草剤
殺虫剤
※必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。
※農薬使用の際は、登録内容をご確認の上、登録使用基準を厳守してください。
※農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害が生じる恐れもあります。
※病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、公共の指導機関にご相談ください。
※医薬用外毒、劇物は、取扱いしておりません。
※当該の農薬を使用した結果、何らかのトラブルが発生してもその責任は負いかねますので、予めご了承ください。