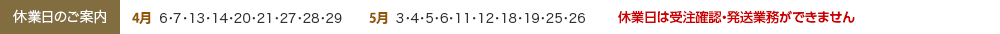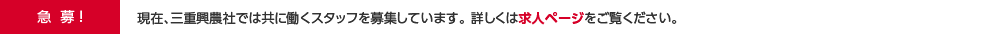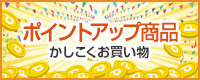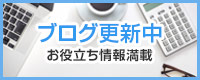タマネギベと病とは(はじめに)
-
タマネギベと病は、たまねぎの重要病害であり、近年多発傾向にある。2016年(平成28年) には、西日本の主要産地において大発生し甚大な被害を被った。その後も、多発する年が多い傾向にある。
-
特に、中晩生品種たまねぎの成長時期にあたる3〜5月に、15℃前後のべと病の発生に好適な気温で、曇雨天の日が続くと発生が増え、被害が拡大する傾向にある。

▲図1 多発被害ほ場(その1)

▲図2 多発被害ほ場(その2)
※(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 提供
タマネギベと病の病原菌
-
タマネギベと病は、糸状菌(かびの仲間)の一つである卵菌類の一種(Peronospora destructor)により発生する。
-
生きた植物(たまねぎ、ねぎなど)の組織にのみ感染する。
-
発病したたまねぎ株の葉の表面には分生胞子が形成(図4)され、これが飛散し病気がまん延する。
-
分生胞子の寿命は最大数日程度である。葉1㎠当たりに形成される分生胞子の数は、数万個と極めて多く、条件が整えば感染株が爆発的に増える。
-
発病した株の葉や根の内部、収穫終了後の残渣の内部には卵胞子が形成される。卵胞子は、高温や乾燥に強く寿命が長く、ほ場に残り次作たまねぎの伝染源になる。

▲図3 発病株(2次感染株)
※(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 提供


▲図4 タマネギベと病分生胞子(顕微鏡拡大)
※(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 提供
タマネギベと病の症状と発生生態
1
苗床・本ぽでの感染と越年罹病株(1次感染株)
-
10〜12月に苗床や定植後のほ場で卵胞子から感染する。
-
感染後、しばらく潜伏した後、翌年の2〜3月頃に発病し症状が現れ、越年罹病株と呼ばれる。
-
葉は萎縮、黄化し、つやがなく、ねじ曲がり、硬くなる(図5)。
-
葉の発病部位に、灰色~灰褐色の分生胞子が作られる。越年罹病株は1,000株に数株程度の発生でも、2次感染株の多発につながる。

▲図5 越年罹病株
2
2次感染株
-
越年罹病株が伝染源となり、3〜5月に好適な気温となり降水量が多い(曇雨天が続く)等の条件が整うと2次感染株(通常見られるべと病の感染株)の発生が増え、急速にまん延する。
-
感染後、2週間前後の潜伏期間を経て発病する。
-
分生胞子は、気温6〜19℃で形成され、最適気温は13〜15℃である。また、気温15℃前後、湿度90%以上で発芽する。
※気温は、3月はやや暖かく、5月はやや肌寒い気温が最適気温である。
-
分生胞子は通常100m、 強風時はさらに広範囲に飛散する。
-
2次感染株は、黄色で大型の長卵形から楕円形をした病斑(函6-1)を生じ、多湿時には霜状のかび(図6-2)が生じることがある。

▲図6-1 2次感染株(黄色で楕円形をした一般的な病斑)

▲図6-2 2次感染株(発生初期の霜状のかび)
※(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 提供
防除方法
耕種的防除と薬剤防除
1
ほ場の選定(連作の回避、ほ場のローテーション等)
-
発生の多いほ場での連作を避ける。
-
夏期に水田作を行い、2年以上栽培の間隔をあける。
2
苗床の消毒(8月)
-
太陽熱による土壌消毒を行う。また、併せて、土譲処理剤による苗床の消毒を行うと効果的である。
3
定植前後の薬剤防除(11〜12月)
-
定植前の苗床や定植直後に予防散布を行うと効果的である。(連作が回避できないほ場などでは特に重要である。)
4
ほ場での薬剤防除・発病株や残さの除去(2〜5月)
<越年罹病株(2~3月頃)>
-
越年罹病株からの2次感染防止のため予防散布を行うことが、特に効果的であり重要である。 (2~3月頃の感染が予想される時期には、気象情報や予察情報(防除情報等)に注意する。)
-
越年罹病株は、発見次第抜き取り、袋等に入れほ場外に持ち出す(分生胞子の飛散防止)。
<2次感染株(3~5月頃)>
-
ベと病は好適条件が揃うと急速にまん延する恐れがあるため、感染前の防除が重要である(予防散布・下図参照)。
-
予防散布が重要であるが、発生を認めた時は、直ちに治療効果が期待される薬剤を散布する。
-
同一薬剤の連用を避ける。なお、散布については、ラベルをよく確認し、収穫前日数、使用回数等に注意する。
-
ベと病に感染したたまねぎ残さ(葉、根)には、卵胞子が多く含まれており、伝染源をなくすためすき込まず、ほ場外へ持ち出し処分する。

タマネギベと病の感染経路と発生サイクル

1
苗床感染(10〜12月頃)
-
苗床の土中や残渣に残る卵胞子により、苗が感染する。感染した株は、秋期に苗床で発病する場合もあり、発病株にできる卵胞子は、次年度の苗床での伝染源となる。
2
本ぽ感染(11〜12月頃)・感染株の発病(翌年2〜3月頃)
-
苗床で感染した株(感染株)の多くは発病せず、定植時に本ぽに持ち込まれ伝染源となる。
-
本ぽの土中や残渣に残る卵胞子によって、健全な株も定植後に感染する。
-
これらの株は、翌年の2~3月を中心に、越年罹病株として発病する。
3
2次感染・発病(3〜5月頃)
-
越年罹病株に形成された分生胞子が、風で飛散し葉表面に付着する。気温や湿度等の条件※1が整うと発芽し、葉内に侵入し2次感染する。感染株は、約2週間※2で発病する。これらの発病株にも分生胞子が作られ、そこから発生が急速に拡大する。
4
卵胞子の形成と土中での生存(5〜10月頃)
-
4〜5月頃に、2次感染株や枯死株に卵胞子が形成される。卵胞子は、残渣や土中で生存し、次作の伝染源となる。
※1 気温は6〜19℃ (最適気温は13〜15℃)で分生胞子を形成、気温15℃前後、湿度は90%で発芽。 分生胞子は、最大数日程度感染能力を持つが、晴天時は数時間程度で感染能力を失う。
※2 潜伏期間: 3月(15〜20日)、4~5月(10〜15日)
タマネギベと病の防除薬剤例
| 薬剤名 | 系統(FRAC) | 種類 | 希釈倍数・使用量 | 使用時期 | 使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| バスアミド微粒剤 | - | - | 20kg/10a | は種14日前まで | 1回 |
| ピシロックFL | テトラゾリルオキシム(U17) | 予防 | 1,000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 |
| フロンサイド水和剤 | 2,6-ジニトロアニリン類等(29) | 予防 | 1,000〜2,000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 |
| オロンディスウルトラSC | F40 + F49 | 治療 | 2,000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 |
| リドミルゴールドMZ | ジチオカーバメート類(M3),無機化合物(M2) | 予防 治療 |
500〜1,000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| ランマンFL | Qil殺菌剤(Qi阻害剤)(21) | 予防 治療 |
2,000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 |
| ザンプロDMFL | QoSl殺菌剤(45)(Qo阻害剤),CAA殺菌剤(40) | 治療 | 1,500〜2,000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 |
| レーバスFL | マンデル酸アシド(40) | 予防 治療 |
2,000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 |